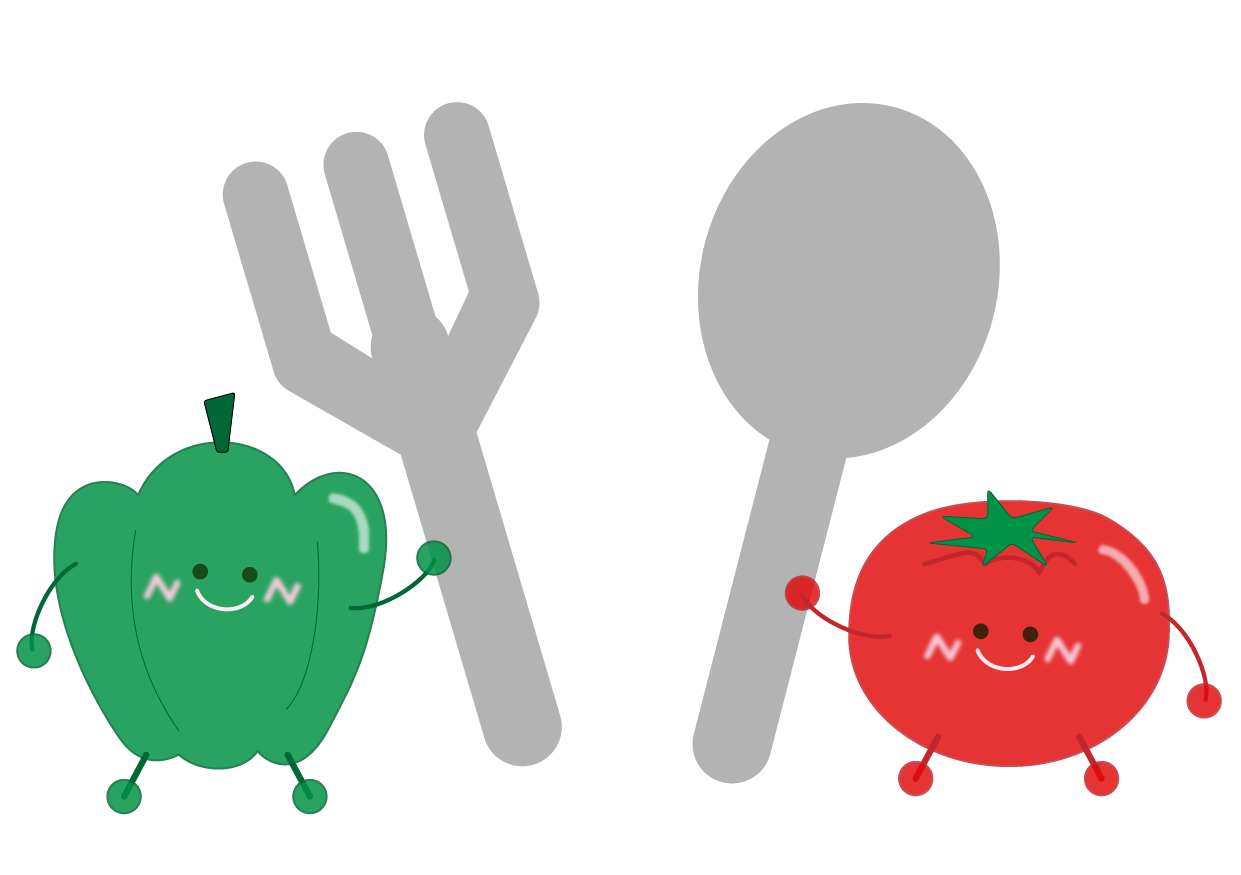食育コラム
- [更新日:2025年5月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
食育とは
食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり 、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てることとされています。
近年、少子高齢化、ライフスタイルの多様化など、食生活を取り巻く環境は大きく変化しています。さらに、食文化の継承、農業体験、地産地消、食品ロスなど、食育に関するテーマは幅広く、複雑になっています。
このような状況を踏まえ、関係機関・団体・生産者や民間事業者との連携・協働をさらに強化し、取り組みの充実を図るとともに、市民の皆様の食への関心を高め、さらなる食育の「実践」を目指していきます。


食育に関する情報を掲載しています。